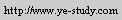hachisukaさんの日記
(SNS全体・外部に公開(Web全体に公開))
-
2017年
03月03日
12:45
-
『シーマン』珍獣的ヒット作が未知の領域を切り拓くのに至るまでを支えた、六つの“仮説”【GDC 2017】
- その他
ゲームメーカーの偉い人から、「新ハードで必ずヒットするゲームを作ってくれ」と頼まれたら、あなたはどの選択肢を選ぶだろうか?
1.市場で既に受けているゲームのシステムを進化させた改良版
2.ハリウッドの有名キャラクターのライセンスを使ったアドベンチャーゲーム
3.かつて見たことのないような“珍獣”的ゲーム。
オープンブックの斎藤由多加氏が選んだのは3だった。そうして出来上がったのが、ドリームキャストを話題性・セールスともに盛り上げ、さらに女性を中心に従来のゲーマー以外の新規顧客の獲得にも成功した『シーマン』である。
現在アメリカのカリフォルニア州サンフランシスコで行われているゲーム開発者向けの国際カンファレンスGDC(ゲーム・デベロッパーズ・カンファレンス)で、同氏が同作の開発について振り返る講演“Classic Game Postmortem: 'Seaman'”が行われた。
DSC_2686
▲文中にもあるように、アメリカ在住経験のある斎藤氏。講演は英語で行われた。
●ランチタイムの冗談から生まれた“シーマン”
そもそもその開発の発端は、斎藤氏が担当するゲームの開発以外に、合併相手の会社が持っていた熱帯魚を鑑賞するアクアリウム系のパソコンソフト(恐らく『アクアゾーン』シリーズ)の開発ラインも走っていた1997年当時の、ランチタイムのちょっとした冗談から始まったのだという。
いわく、熱帯魚の研究とリサーチには手間がかかる割に、アクアリウム系のソフトはそれをただ鑑賞することに終始する。そうではなく、手足が生えたり、魚なのに陸地に上がったりするぐらいの変化を見せるのがエンターテインメントなんじゃないか、自分ならああいうソフトは作らないね……と。
これは恐らく社長として鑑賞系ソフトに一定の需要があるのは理解した上での話で、冗談がゆえの無茶な難癖なのだが、それが受けた。話が盛り上がったついで、斎藤氏は話を膨らませていく。魚だって人間に毎日ジロジロ見られるのは嫌なはずだ、もし魚が喋れるなら荒井注のように「何見てんだよ!」などと言うに違いない……。そして喋れるんなら人間の顔を持っているんだろうと発展させた所で、子供の頃に買ったシーモンキーのパッケージ絵の不気味さを思い出し、こう言ったそうだ。「さしずめシーモンキーならぬシーマンだな」。
DSC_2663
▲確かに怖い。
●「好きの反対は嫌いではない」
そのやり取りが妙に記憶に残った斎藤氏は、その冗談から生まれた“シーマン”の姿をスケッチし、夫人に見せたところ、気持ち悪がられてしまう。人によっては、ここでシーマンの命は尽きていたかもしれない。
DSC_2665
だがしばらくして逆に、あの企画はどうなったのか、あんな気持ち悪い企画はやるべきだと言われたことがすべての運命を変えた。確かに最初気味悪がったが、それは興味のありようのひとつだったのだ。ネガティブな感情も、無関心と比べると一定の誘引力があるのは間違いない。「好きの反対は嫌いではない。無関心だ」。その気付きについて斎藤氏は、同氏のその後のキャリアそのものを変えた出来事だったと語った。となればこの気持ち悪いゲームも、その異形ゆえに関心を集められるのかもしれない。
●道なき迷いを仮説を軸に乗り切れ
そうしてサンフランシスコの対岸の町バークレーでプロトタイピングが始まった『シーマン』。ある日セガから新ハードのためにかつてない新しいゲームを求められた斎藤氏は、その場でMac Powerbookに入っていた『シーマン』のプロトタイプを披露。その気持ち悪さが受けたことで、本格的な開発がスタートする。
本開発にあたっては、従来のヒット作の常識から外れた“3つの逆”を重視したという。それは第一に、キャラが可愛くないこと、第二にファンタジーの話ではなく、むしろ虚構的な人面魚がユーザーの周囲の現実について話すこと。そして第三に、プレイヤーがテレビの中のキャラクターに自分自身を重ね合わせるのではなく、むしろキャラクターがテレビの中からキャラクターがプレイヤーの部屋を覗き込んでいるような感覚がすること。
では、どうやってその“逆”をやり通した上で、成功に導くことができたのか? 斎藤氏はここで、まったく新しいものを作るという作業は、道なきが故にたびたび襲ってくる“迷い”との戦いであると述べる。そして、その上でその迷いを乗り越えるために必要だとするのが“仮説”だ。ちなみに当時は明確には仮説の効能について気付いておらず、これは今回現在の視点から振り返るにあたって改めて認識したんだとか。
●五つの“仮説”
第一の仮説は、「好きであれ嫌いであれ、自分自身に無関心な人はいない」というもの。シーマンとの会話で何を話させるか、テーマなしにあちこちに話題が飛べば、プレイヤーはつきあってくれなくなる。そのためには誰もが興味を惹くだろう強いテーマが必要だが、ファンタジーなどに興味がない人はいても、自分に対して完全に無関心ということはないだろうというのがその理由。
第二の仮説は、「迷ったら女性的な仕様を選ぶ」。セガのゲームに興味がないような人に購入してもらうにあたって、母性本能や、必要とされると返したくなる人の性を利用しようというもの。シーマンの育成は毎日定期的に相手をしなければならず、ある意味自己中心的な性質を持つに至ったわけだが、それによってドリームキャストごと旅行先に持っていって世話をするという人も出た。
第3の仮説は、「広告でアピールするにあたって、技術でアピールするのではなく“ペット育成”という昔ながらの枠組みを利用する」ということ。ゲームに興味がない人も取り込もうというのだから、ゲーム的・技術的な売り文句は効果を発揮しない。斎藤氏は「エンターテインメントは合意形成が必要」ということを繰り返し述べていて、未知のものへの警戒心を乗り越えるには、その人の中にあるものとうまく結びついて理解してもらう必要があるからだ。実はシーマンの広告には音声認識などの用語は一度も入ったことがないという。
DSC_2673
第4の仮説は、「シーマンの声は有名な俳優や声優であってはならない」。結果的にシーマンの声は日英ともに斎藤氏本人が演じることになるのだが、声とセリフ回しが非常に重要なゲームにあって、気が済むまで何回ものリテイクが可能で、かつ(演技力はともかく)ディレクターとして欲しいニュアンスをこの上なく理解している唯一の人物。さらにシーマンという存在そのものをミステリアスなものに維持するのにも役立っている。
一方第5の仮説は、それに対して「有名な代弁者が必要」という、一見矛盾しそうなもの。ナレーターとして日本版は大物俳優の細川俊之、英語版はなんとスポック俳優のレナード・ニモイが演じている。これは、ミステリアスな存在であるシーマンと、プレイヤーを繋ぎ、かつ安心させるような機能を持つ。
かくして『シーマン』は社会現象ともなったが、実はセガは斎藤氏の語っていた“仮説”をそこまで信用していなかった節があるという。それは付属マイクの発注不足という形で表面化したが、逆に市場の不足がかえって神話性を高めることになったというのだから面白い。
DSC_2676
●仮説は前に進むために、前に進むのは実現するために
斎藤氏は最後の“仮説”として、“仮説”とは、まだほとんど定義されていない未知のものを作るにあたって、それに基づいてさまざまな関係者からの質問に答えることで、それが正しかろうと誤っていようとも、リーダーとして一貫性を持たせチームを前に押し進め、同時にゲームデザイナーとして自分の信念を支えるものと位置づけた。
しかし、“仮説”以上に重要なものだとしたのが、それを実行すること。「あなたと同じぐらいユニークなアイデアに至る人は何百人もいます。自分の真の強さを見せる方法があるとすれば、それは仮説を現実のものにすることです。『シーマン』が何かを勝ち得たのだとすれば、このクレイジーなアイデアを何とか製品にし、市場に届けられたということです。だから既にある慣習から外れることを恐れないでください。流れに逆らって泳ぐんです。未来を予測しようとするのではなく、未来を作り出すんです」と激励し、講演を締めくくった。
アラド RMT- 総アクセス数(1,493)
 拍手(0)
拍手(0) お気に入り(0)
お気に入り(0)
最近の日記
- 予想外なユニット続出 アイマス765ミリオン合同ライブ「ハッチポッチフェス」DAY1レポート
- 予想外なユニット続出 アイマス765ミリオン合同ライブ「ハッチポッチフェス」DAY1レポート
- PS4 復讐、依存、妄想、恋心──『追放選挙』の登場人物たちに隠された裏の顔。選挙に利用するべきか否か
- 『シーマン』珍獣的ヒット作が未知の領域を切り拓くのに至るまでを支えた、六つの“仮説”【GDC 2017】
- Xbox One版「アケアカNEOGEO」の第1弾が明日発売。「ビッグトーナメントゴルフ」と「ワールドヒーローズ」の2タイトルを同時リリース
- PS4「ファーミングシミュレーター17」農場での働き方や農業機械にフィーチャーした6本の動画が公開!
- “PlayStation Store ゲームアーカイブス”月間ランキング(2017年1月度)発表! 1月も『バイオハザード』関連作が好調
各月の日記
- 2026年2月の一覧
- 2026年1月の一覧
- 2025年12月の一覧
- 2025年11月の一覧
- 2025年10月の一覧
- 2025年9月の一覧
- 2025年8月の一覧
- 2025年7月の一覧
- 2025年6月の一覧
- 2025年5月の一覧
- 2025年4月の一覧
- 2025年3月の一覧
- 2025年2月の一覧
- 2025年1月の一覧
- 2024年12月の一覧
- 2024年11月の一覧
- 2024年10月の一覧
- 2024年9月の一覧
- 2024年8月の一覧
- 2024年7月の一覧
- 2024年6月の一覧
- 2024年5月の一覧
- 2024年4月の一覧
- 2024年3月の一覧
- 2024年2月の一覧
- 2024年1月の一覧
- 2023年12月の一覧
- 2023年11月の一覧
- 2023年10月の一覧
- 2023年9月の一覧
- 2023年8月の一覧
- 2023年7月の一覧
- 2023年6月の一覧
- 2023年5月の一覧
- 2023年4月の一覧
- 2023年3月の一覧
- 2023年2月の一覧
- 2023年1月の一覧
- 2022年12月の一覧
- 2022年11月の一覧
- 2022年10月の一覧
- 2022年9月の一覧
- 2022年8月の一覧
- 2022年7月の一覧
- 2022年6月の一覧
- 2022年5月の一覧
- 2022年4月の一覧
- 2022年3月の一覧
- 2022年2月の一覧
- 2022年1月の一覧
- 2021年12月の一覧
- 2021年11月の一覧
- 2021年10月の一覧
- 2021年9月の一覧
- 2021年8月の一覧
- 2021年7月の一覧
- 2021年6月の一覧
- 2021年5月の一覧
- 2021年4月の一覧
- 2021年3月の一覧
- 2021年2月の一覧
- 2021年1月の一覧
- 2020年12月の一覧
- 2020年11月の一覧
- 2020年10月の一覧
- 2020年9月の一覧
- 2020年8月の一覧
- 2020年7月の一覧
- 2020年6月の一覧
- 2020年5月の一覧
- 2020年4月の一覧
- 2020年3月の一覧
- 2020年2月の一覧
- 2020年1月の一覧
- 2019年12月の一覧
- 2019年11月の一覧
- 2019年10月の一覧
- 2019年9月の一覧
- 2019年8月の一覧
- 2019年7月の一覧
- 2019年6月の一覧
- 2019年5月の一覧
- 2019年4月の一覧
- 2019年3月の一覧
- 2019年2月の一覧
- 2019年1月の一覧
- 2018年12月の一覧
- 2018年11月の一覧
- 2018年10月の一覧
- 2018年9月の一覧
- 2018年8月の一覧
- 2018年7月の一覧
- 2018年6月の一覧
- 2018年5月の一覧
- 2018年4月の一覧
- 2018年3月の一覧
- 2018年2月の一覧
- 2018年1月の一覧
- 2017年12月の一覧
- 2017年11月の一覧
- 2017年10月の一覧
- 2017年9月の一覧
- 2017年8月の一覧
- 2017年7月の一覧
- 2017年6月の一覧
- 2017年5月の一覧
- 2017年4月の一覧
- 2017年3月の一覧
- 2017年2月の一覧
- 2017年1月の一覧
- 2016年12月の一覧
- 2016年11月の一覧
- 2016年10月の一覧
- 2016年9月の一覧
- 2016年8月の一覧